次回の自民党総裁選に立候補しているコバホークこと小林鷹之氏の発言が大きな話題を呼んでいます。
その発言とは、「いま入って来ている外国人労働者は移民ではない」。
「実質的には移民じゃないか」「定義のすり替えだ」と批判が相次ぐ一方で、「法的な立場からすれば正しい」「長期的な社会設計を重視する現実論だ」と擁護する声も。
動画の内容及び炎上のポイントについてまとめます。
◆ 発言の経緯:「移民政策には反対」だが「今は移民ではない」

小林氏はインタビュー(動画44:40頃)で、「移民政策には反対」と明言しました。
過去、6年前の入管法改正時にも「目指すべき社会像がない」として反対に回ったと語っています。
そのうえで問題となったのが次の一言です。
「今入ってきている外国人労働者は移民ではない。定義が違う」
これがネット上で「開き直り」「国民感情を無視」と批判を浴び、炎上の火種になりました。
>いま入って来ている外国人労働者は移民ではない
— red super (@redsuper9) September 27, 2025
たしかに、「移民」として来ているわけではないです。
入国するときはビザがあるでしょうが、現場から失踪して、不法滞在する「犯罪者」になっています。
これに対応しないのは政府の怠慢です。https://t.co/MK6IX5Hop9
◆ 小林氏の基本ロジック
小林氏の主張を整理すると、以下の通りになります。
- 移民拡大には反対
- 目的も社会像も示されずに「人手不足だから」という理由だけで大量に受け入れるのは誤り。
- 「無方針な拡大」は文化・伝統に長期的な影響を及ぼす。
- 現行制度は「移民」ではない
- 在留資格や受け入れ枠組み上、いまの日本は「移民政策」ではない。
- 「移民ではない」と繰り返し強調。
- 日本の“自立”を優先
- 外国人に依存せずに回る社会構造を目指す。
- そのために 賃上げ・労働環境改善・自動化/AI・ロボット導入 を推進。
- 選別と秩序
- 高度専門人材は歓迎。
- ルール違反をする外国人には厳格対応。
- まじめに働く人を守るためにも、秩序が必要。
- 長期的影響への警戒
- 「5年先は変わらなくても、10年・20年・30年後には文化・慣習に影響する」
- 伝統や自律的規範を守り、次世代に引き継ぐのが保守の使命。
◆ ネットの反応:真っ二つに割れる世論
小林氏の「移民ではない」発言をめぐり、SNSや掲示板では賛否が激しく対立しています。
批判的な声
- 「どう見ても実質移民。現場感覚とズレすぎ」
- 「定義の問題に逃げている。言葉のトリックだ」
- 「高度人材歓迎って言うけど、結局は受け入れ容認じゃないか」
- 「国民が怒っているのは秩序不在と不透明感。そこに答えていない」
擁護的な声
- 「国際法上、いまの制度は“移民”ではないのは事実」
- 「移民拡大に慎重で、自立を優先という方針は一貫している」
- 「自動化や賃上げに言及した政治家は少ない。現実的な長期戦略」
- 「感情論ではなく、定義と政策のすみ分けをしているだけ」
◆ 炎上が拡大する3つの理由
- 「定義」と「生活実感」の乖離
- 法的には「移民」ではないかもしれないが、地方では外国人労働者が不可欠になっている。
- 国民の「もう移民社会になっている」という実感と、小林氏の「移民ではない」が噛み合わなかった。
- 二枚舌に聞こえる構造
- 「移民反対」と言いながら「高度人材は歓迎」と述べる姿勢が、「結局受け入れるんだろ」と批判されやすい。
- 「依存縮小」と「受け入れ容認」が同居するロジックに矛盾を感じる人も多い。
- 過去の自民党対応への不信感
- 小林氏は「6年前の入管法改正は結論ありきだった」と回顧。
- だが「ならなぜ止められなかった?」という責任追及が再燃している。
◆ 小林氏が描く「移民に頼らない社会像」
炎上の裏で注目すべきは、小林氏が語った2050年国家戦略です。
- 外国人に頼らなくても成り立つ社会をつくる
- そのために必要なのは
- 日本人雇用の拡大(賃上げ・労働環境整備)
- 自動化・AI・ロボット導入(省人化)
- 高度人材の選別的受け入れ
- 秩序あるルール運用
小林氏の構想は、短期的な人手不足対策よりも長期的な自立と文化維持を優先する立場のようです。
◆ では、なぜ炎上するのか?
理由はシンプル。
国民が求めているのは「定義」ではなく「生活実感」への回答。つまり、現実問題を何とかしてほしいと感じているわけです。
- 地方ではすでに外国人労働者が不可欠な存在。
- 一方でトラブルやルール違反が報じられると、不安も増幅する。
- そこで「移民ではない」と言われると、「いや、現実を見ろ」となる。
つまり炎上の本質は「政策そのもの」ではなく、メッセージの伝え方にあるのでしょう。
◆ まとめ:保守的現実主義か、すり替えか
小林鷹之氏の「移民ではない」発言は、保守的現実主義とも定義のすり替えとも取れる。
彼の真意は「無方針な拡大は拒否」「自立を最優先」「高度人材は歓迎」「ルールは厳格」というシンプルなものだ。
だが、国民の生活実感に寄り添わなければ、炎上は避けられない。
総裁選という舞台で問われているのは、単なる法的定義ではなく、日本社会の未来像をどう描くかだろう。
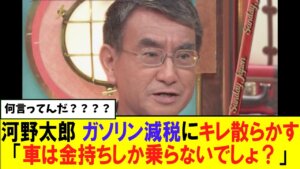






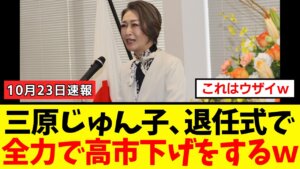
コメント