2025年10月4日、自民党総裁選の結果が発表され、高市早苗氏が新総裁に選出されました。
その瞬間、あるテレビ朝日の記者が生放送中に明らかに表情を崩したとして、SNS上で大炎上。
動画のコメント欄やX(旧Twitter)では、「報道の中立性とは何だったのか」「推しが負けたファンの顔だった」といった声が殺到しました。
■ 小泉進次郎“推し”の空気が充満していた番組構成
問題となったのは、テレビ朝日系の報道番組。
番組開始直後からコメンテーターや記者が、
「小泉氏は国民的人気が高い」
「高市氏は安定感に欠ける」
といったコメントを繰り返し、明らかに小泉氏有利のムードで進行していました。
SNS上でもこの段階で既に「また始まった偏向報道」「高市叩きが露骨すぎる」と批判が相次いでいました。
視聴者の多くは、番組が“結論ありき”で台本を組んでいたのではないかと感じたようです。
■ しかし情勢は一変…高市氏が逆転勝利
当初は議員票で優位に立つとみられていた小泉陣営でしたが、党員票の開票が進むにつれて状況は逆転。
高市氏が全国の党員票を軸に支持を拡大し、最終的に議員票までも取り込み逆転勝利を果たしました。
その瞬間、スタジオの空気は一変。
画面に映ったテレ朝の政治記者は、肩を落とし、顔を引きつらせて沈黙。
普段は自信満々にコメントしていた姿とのギャップが強烈だったため、
ネット上では「感情丸出し」「あれはもう記者じゃなくてファンの反応」と揶揄される事態になりました。
■ SNSでは「偏向報道の象徴」として瞬時に拡散
高市勝利の瞬間を切り取った映像やスクリーンショットは、X上で瞬く間に拡散。
「テレビが推す人は大体負ける法則、また発動したな」
「高市さんが勝った瞬間の記者の顔、まさに歴史的瞬間」
「オールドメディアが国民の感覚とどれだけズレてるか一目でわかった」
といったコメントが数万件単位で共有され、
“報道機関の中立性”というテーマが再び大きな議論を呼びました。
一方で、番組内では最後まで小泉氏を擁護するようなトーンが続き、
記者の表情変化と合わせて「これが日本の報道の現実」と冷ややかな見方も多く見られました。
■ オールドメディアへの信頼が崩れる“象徴的な事件”
この一件がここまで話題になった背景には、長年にわたるマスコミへの不信感があります。
特に政治報道においては、特定の候補を持ち上げ、他方を不当に貶めるような解説が繰り返されてきました。
そのため今回の「記者の顔が曇る瞬間」は、国民の中でくすぶっていた不信と反感を一気に爆発させたとも言えます。
ネット上では、
「報道を名乗るなら感情を隠せ」
「公平な解説者が推しの敗北で動揺するなんて論外」
といった意見も噴出。
“報道は中立であるべき”という基本原則が改めて問われる出来事になりました。
■ 情報の主導権が「テレビから国民へ」移った瞬間
動画の後半では、「この総裁選は単なる人事ではなく情報環境の転換点だ」と指摘されています。
つまり、SNSやネットの時代では、もはやテレビが世論を誘導することはできないということです。
かつてはテレビが「国民的人気」という言葉を使えば、それが世論のように見えました。
しかし今や、ネット上の一般有権者が情報を直接共有し、「誰が本当に信頼できるか」を自ら判断する時代に変わっています。
高市氏の勝利は、そうした“情報の民主化”を象徴する結果だったといえるでしょう。
テレビが作り出した幻想の人気よりも、地に足のついた政策評価と現実感が選ばれたのです。
■ 筆者の考察:これは“政治の勝利”以上に“国民の勝利”
今回のテレ朝報道騒動を通じて見えてきたのは、政治家同士の争いではなく、「国民 vs オールドメディア」という構図です。
メディアが作り出した“人気”や“物語”が通用しなくなり、国民が自分の判断でリーダーを選び取った。
その象徴が高市早苗氏の勝利であり、そして“記者の顔が曇る”というシーンは、その歴史的瞬間を象徴していました。
この出来事は、報道の在り方を根本から問い直すきっかけになるでしょう。
公平さを欠いた報道は、もはや視聴者に見抜かれ、SNSで検証され、批判される時代です。
今後、メディアが再び信頼を取り戻すには、
「誰かを持ち上げる報道」ではなく、「事実を淡々と伝える姿勢」を貫くしかありません。
■ まとめ
- テレ朝記者が高市早苗総裁誕生の瞬間に表情を崩し、ネットで大炎上
- 番組全体が小泉進次郎氏“推し”の構成で偏向報道と批判
- 高市氏の逆転勝利でスタジオは凍りつき、記者の感情が露呈
- SNSでは「メディアの終焉」「国民の勝利」との声多数
- 今回の総裁選は、情報の主導権がテレビから国民に移った象徴的な事件
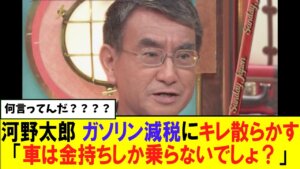






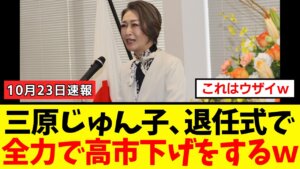
コメント