2025年10月、メルカリが大きな決断を下しました。
それが、隙間バイト事業「メルカリハロ」のサービス終了です。
「利用者1,200万人突破」「業界ナンバーワンの新規登録数」と好調をアピールしていたのに、
なぜたった約1年9ヶ月で撤退を決めたのか?
その裏には、“タイミー”という圧倒的王者との「残酷な現実」がありました。
■ メルカリハロとは?急成長した“隙間バイト”アプリ
メルカリハロは、2024年3月に始まったスポットワーク事業(単発バイト)です。
「タイミー」などと同じく、好きな時間に働ける“スキマバイト”を提供していました。
・2025年6月時点で登録者数1,200万人突破
・新規登録数は業界ナンバーワン(PR TIMESより)
・C2C(個人間取引)で培ったメルカリブランドを活かし、参入直後から話題に
ところが、その約4ヶ月後——
2025年10月14日、「サービス終了のお知らせ」が公式に発表されました。
■ データが示す「圧倒的な差」:タイミー vs メルカリハロ
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」に登録されている就職実績を見ると、
両社の差は“数字で一目瞭然”です。
| サービス名 | 2024年度 就職者数 | 登録者に対するマッチング率 |
|---|---|---|
| タイミー | 約1,805万3,000人 | 約180% |
| メルカリハロ | 約94万7,000人 | 約7.8% |
つまり、マッチング成功率はタイミーがメルカリの20倍以上。
利用者が多くても、実際に“働ける”機会が少なければ意味がありません。
■ 売上は約13億円規模、それでも撤退の決断
動画内では、メルカリハロの収益構造を丁寧に試算しています。
- 平均時給:1,300円
- 1回あたりの労働時間:3.5時間
- 手数料:30%
- 年間就職者数:94.7万人
これを単純計算すると、
1,300円 × 3.5時間 × 0.3 × 947,000件 ≒ 約13億円の売上になります。
それなりに大きな数字ですが、メルカリ全体から見ればわずか0.6%程度の規模。
メルカリの主力3事業と比べると、その差は歴然です。
| 事業名 | 売上収益 | 割合 |
|---|---|---|
| メルカリマーケットプレイス(C2C) | 1,112億円 | 57.7% |
| フィンテック(メルペイなど) | 385億円 | 19.9% |
| メルカリUS | 364億円 | 18.9% |
| メルカリハロ | 13億円 | 0.6% |
経営的には「費用対効果が低い」と判断せざるを得なかったのです。
■ メルカリが抱えた最大の弱点:“法人営業力”
メルカリの本体ビジネスはC2C(個人間取引)です。
個人ユーザー同士の出品・購入をマッチングするプラットフォーム運営が中心で、「企業への直接営業(B2B)」には強くありません。
一方で、タイミーは法人営業が命。
全国に営業担当741人を配置し、飲食・小売・物流など各業界ごとに専門チームによるコンサルティング営業を行っています。
メルカリの社員は全体で約2,200人。
タイミーと同レベルの営業組織を作るには、全従業員の3分の1を営業部門に回す必要がある計算です。
この「営業力の構造的な差」が、撤退を決定づけた要因でした。
■ タイミーが“強すぎる”理由:即日給与とデータ戦略
タイミーは単なる「バイトマッチングアプリ」ではありません。
・勤務直後に給与が即受け取れる「即払いシステム」
・業界別データを活かしたコンサル型営業
・企業とワーカーの相互評価データによるマッチング精度向上
さらに、即日払いを可能にするために立替資金100億円以上を保有しており、
これは新規参入組にとって大きな参入障壁となっています。
■ 他社も続々撤退:リクルート・パーソルも苦戦
実はメルカリだけではありません。
大手人材企業もこの“スキマバイトの壁”に阻まれています。
- リクルート:2025年3月、「タンワーク」開発中止を発表
- パーソルHD:「シェアフル」運営中だが、就職者数は約21.5万人(タイミーの1%程度)
つまり、タイミーがほぼ独占状態。
リクルートやメルカリといった大手でも勝てないほど、“法人営業+データ運用”の仕組みが完成されているのです。
■ 隙間バイト市場はどこまで広がるのか?
タイミーの試算によると、
「隙間バイトプラットフォーム市場」は最大3.9兆円の潜在規模があるとしています。
しかし、動画では「そこまで大きくはないのでは」と冷静に分析。
現実には、
・参入障壁の高さ
・法人営業の負担
・競合の寡占化
これらを考えると、誰でも勝てる市場ではないようです。
■ メルカリが得た“痛みを伴う学び”
メルカリハロの撤退は、失敗ではなく「貴重な経営判断の結果」とも言えます。
動画では次のようにまとめています。
「市場の大きさと競合の強さを正確に見極め、
自社の強みをどこで活かすかを見定めることが重要。」
メルカリはC2Cの王者。
法人営業の泥臭い世界ではなく、得意分野に集中するという決断を下したといえるでしょう。
■ まとめ:メルカリ撤退の真相と今後の教訓
- メルカリハロの就職者数はタイミーの1/20以下
- 営業力の差が最大の敗因
- 事業規模は全体の0.6%、収益性も低い
- リクルートやパーソルも苦戦中、タイミーが独占市場に
結果として、メルカリは「戦略的撤退」を選びました。
一方で、タイミーは圧倒的な営業体制と即日給与システムで市場を掌握。
“泥臭い現場主義”が、最終的な勝敗を分けたといえるでしょう。
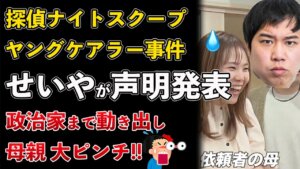

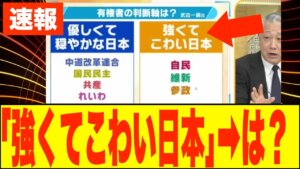



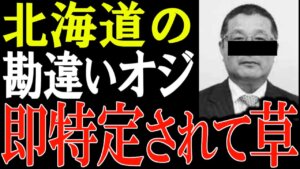
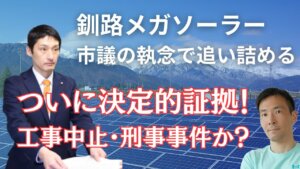
コメント